働く女性の皆さんこんにちは。瀧澤裕子です。
日本の挨拶はお辞儀(礼)が正式になります。お辞儀の歴史を紐解いてみましょう。
1 お辞儀の歴史とは?

お辞儀は「魏志倭人伝」の中に
「大人に対して拍手をし、跪いてお辞儀をすること」
慎みや敬う姿を表す、と記されてあります。
「跪いてお辞儀をする」は現代の座礼に似たことが行われていたと考えられます。
ただし、その後、天武天皇が唐から伝わった礼法を取り入れて、座礼から立礼が一般的になりました。
平安時代の公家は下位者に対してお辞儀をすることはありません。
下位者である、衣紋者(平安時代の正装である束帯や十二単を着付ける者)が公家に対してお辞儀をするときは、
ひざの上に手を置いたままか、手の平を上にして、手の甲を床につけて頭を下げる形をとっていました。
これは、身分の高い人の衣装に触れる手のひらが汚れないようにとの配慮の形です。
鎌倉時代になると、武士が主人公になってきます。
文化も作法も「質実剛健」なものになります。
将軍など大広間で遠くの人にも儀礼を尽くして挨拶することが、自身の存在を主張することなので、
所作も大きくなり、しっかりと床に手をついて、深く頭を下げるものとなりました。
それに相反するかのように、安土桃山時代、侘び茶が形成されていくと、
狭い茶室での身振りの小さなお辞儀が生まれます。
肩肘張った形式的なものではなく、心が通じ合い相手を思いやる行為として、
自然な形のお辞儀と変化していったのです。
2 美しいお辞儀を身につけよう

お辞儀には、立礼と座礼があります。
それぞれに、真礼、行礼、草礼の三種類の礼があります
立礼とは、立ってのお辞儀で、座礼とは、畳の上に正座してのお辞儀です。
ビジネスの場面では、立礼が中心となります。
美しい立礼には以下のポイントがあります。
・姿勢が良い
・腰から折る
・手は指を揃えて、真横に降ろして
・「礼三息」を忘れずに
・最初と最後に目を合わせる
・深さはTPOに応じて
これらを少し意識して、日頃から美しいお辞儀を心がけたいものですね。


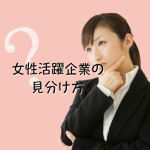


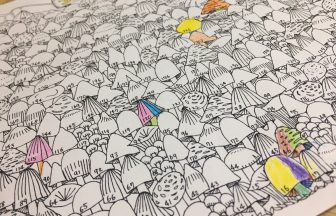






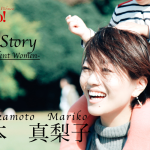
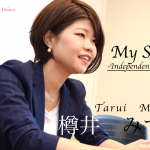


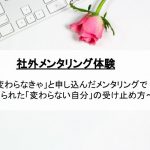




この記事へのコメントはありません。